- 公務員を辞めたいけど、その後の末路が不安…
- 公務員退職後の具体的な生活やキャリアってどんな感じなんだろう?
- 実際に公務員を辞めた人の失敗談や成功体験などを知りたい
このような悩みはありませんか?
公務員は安定の職業として人気で、退職する人も民間企業と比べると少ないです。一方で、公務員の働き方に合わず、退職して別の道を選択する人も多くなってきています。
また、公務員を辞めることが必ずしもネガティブな末路になるわけではありません。
この記事では、元自治体職員の私が、公務員を辞めても大丈夫な理由や退職後のリアルについて、自身の体験談も交えながら本音で解説します。
公務員を辞める前にすべきことも紹介するので、これから公務員を辞めてキャリアチェンジを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 公務員事務職として約10年勤務
- 将来のキャリアに不安を感じ、プログラミングスクール受講
- 後悔したくないと思い、勇気を出して公務員を辞め、36歳未経験でエンジニアに転職
- テレワークやフレックス勤務など自由度の高い働き方をに手に入れる
- 現在はエンジニアのほか、PMやコンサルタント業務も担当
おすすめの転職エージェント
公務員を辞めても末路ではない3つの理由

公務員を辞めても、人生の末路にはならないので心配無用です。その主な理由を3つ紹介します。
- 後悔しない人生を生きられるから
- 備えておけば経済的には問題ないから
- 公務員に再度戻ることも可能だから
1. 後悔しない人生を生きられる
公務員という安定した道を手放す決断には大きな勇気がいりますが、決して「末路」ではありません。
自分が本当にやりたいことや、興味関心がある分野に挑戦することで、後悔のない自分らしい人生を歩めます。
そして、新たな道に進むなら、なるべく若くて、早いほうがいいです。
人生は一度きりなので、迷ったらやってみるくらいで丁度いいかもしれません。
公務員を辞めることで、安定だけでは得られない成長や、内面的な充実感を得られるきっかけにもなります。
2. 備えておけば経済的には問題ない
公務員は失業給付を受けられないので、「辞めたら経済的に苦しくなるのでは」と不安に感じるかもしれません。
しかし、公務員を辞める前に、しっかりと資金を準備しておけば、金銭面の不安はなくなります。
具体的には、貯蓄額や退職金の見込み額を確認し、退職後の収支計画を事前に立てておくことです。
このように実際に数字で状況を把握することで、漠然とした不安を解消でき、安心して辞められるでしょう。
3. 公務員に再度戻ることも可能
一度公務員を辞めたとしても、再び公務員として働く道が閉ざされるわけではありません。
退職後も別の自治体や国家公務員の採用試験を受け直すこともできます。
近年は公務員も人手不足により、採用方法にも変化しています。例えば、年齢制限の緩和や採用枠の拡大などにより、以前に比べて採用のハードルも下がってきています。
そのため、一度民間企業へ転職しても再度公務員へ復帰することも十分可能です。
今は多様なキャリアパスが認められる時代です。公務員を辞めたからといって、それで「終わり」になるわけではありません。
よくある公務員を辞めた後の誤解5選
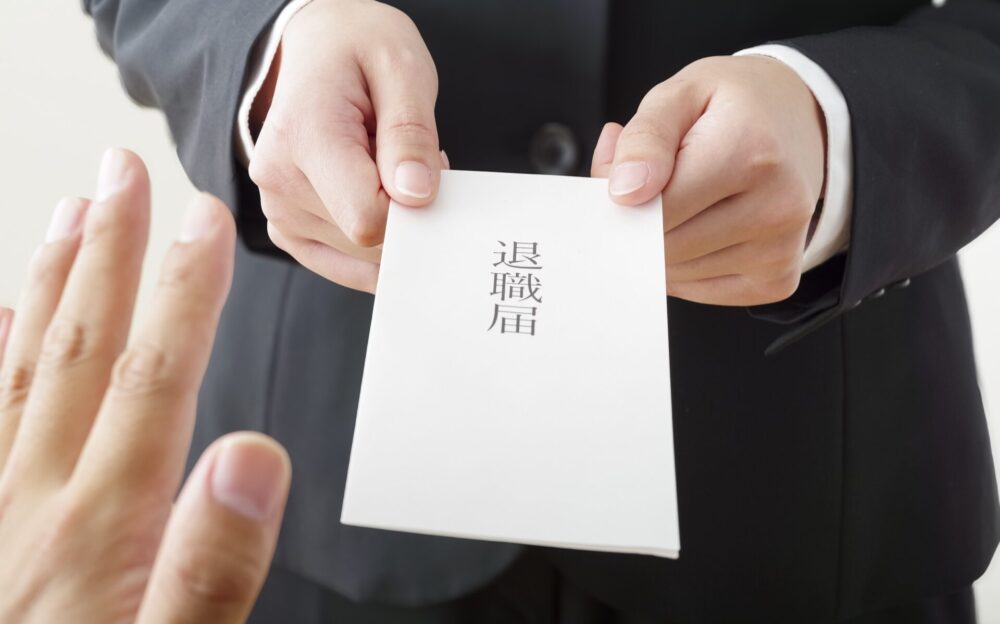
ここでは、公務員を辞めたあとによく語られる誤解と事実について、一つずつ解説していきます。
- 社会的信用が下がる
- 仕事の安定性がなくなる
- 失業保険がもらえず困窮する
- 民間企業へ転職すれば給料が上がる
- 転職して仕事へのやりがいが増える
社会的信用が低下する
「公務員でなくなる=社会的信用が下がる」という考えは誤解です。
確かに、公務員は倒産の心配がない職業として、一定の信用があります。しかし、民間企業でも社会的信用がなくなるわけでなく、通常の生活で困ることはありません。
また、これまでのキャリアで培ってきたスキルや実績、人脈、さらに転職後の活躍によっても信用は築かれていきます。
とはいえ、ローンの申請や審査では、公務員の方が有利なケースがあるのも事実です。
そのため、近いうちに住宅購入などを検討している場合は、退職前に手続きを済ませておくと良いでしょう。
仕事の安定性がなくなる
公務員に比べて民間企業は不安定だと思われがちですが、民間にも経営が安定していて、長期的に安心して働ける企業も多く存在します。
また、終身雇用が崩れつつある現代では、公務員であっても安泰とは限りません。
真の安定は、特定の組織に依存するのではなく、自身の市場価値を高め、変化に対応できる能力を持つことです。
「公務員だから安定」といった考え方にこだわらず、自分自身のスキルや経験を積み上げる方が大切といえます。
失業保険がなくて困窮する
公務員は雇用保険制度の対象外であるため、失業保険がありません。
しかし、在職期間に応じて、退職手当が受け取れます。退職手当と貯蓄額を合算して、どれくらいの期間働かなくても生活できるか把握しておくと安心です。
公務員が失業保険がないからといって、すぐに困窮するわけではないといえるでしょう。
ただし、退職手当は勤続年数によって変わるので、勤務期間が1〜2年の場合は微々たるものになります。
そのため、十分な貯蓄がない場合は、転職先が決まるまで退職しない方が賢明です。
民間へ転職すると給料が上がる
公務員から民間へ転職しても、給料が上がるとは限りません。
給与水準は、転職先の業界、職種、企業の規模、そして自身の経験やスキルによって大きく変わります。

実際、私は未経験業界に転職したため、給料は約40%下がりました。
民間企業では、公務員の年功序列による給与体系とは異なる評価基準が適用されるのが一般的であるため、自身の市場価値を正しく把握し、戦略的に転職活動を進める必要があります。
年収アップ転職を目指すなら、高年収求人の紹介に強い転職エージェントであるJACリクルートメントがおすすめです。
\ハイクラス転職満足度 7年連続No.1/
仕事へのやりがいが増える
民間の方がやりがいが増えるというのも誤解です。
やりがいを感じるかは、仕事内容や職場の人間関係、個人の価値観など、多くの要因に左右されます。
民間に転職しても、希望の仕事に就けなかったり、職場の文化が合わなかったりすれば、やりがいを感じにくいでしょう。
一方で、民間企業では成果が売上などの数値で表れたり、公務員よりも身につけたスキルや知識が市場価値に直結したりする効果があるのも事実です。
やりがいは環境や自身の適性によるところが大きいため、興味関心のある分野を選ぶことが大切です。
公務員を辞める前にやっておくべきこと


公務員を辞める決断は、その後の人生設計に大きな影響を与えます。勢いで退職して後悔することのないよう、事前の準備が大切です。
特に、退職後の生活基盤の安定やスムーズなキャリアチェンジのため、最低限以下の3つの点を押さえておきましょう。
- 生活防衛資金を貯める
- 退職予定日を決める
- 次の転職先を確保する
1. 生活防衛資金を貯める
まずは、生活防衛資金をしっかり準備しておくことが重要です。
公務員の収入が途絶えた後、次の仕事が見つかるまでの生活費、転職活動にかかる費用など、予期せぬ支出に備えるための資金です。
目安として生活費の3ヶ月分、可能であれば半年から1年分を用意しておくと、気持ちに余裕が生まれます。
もちろん、退職から次の転職先の勤務開始日までの間が短い場合は、そこまで準備する必要はありません。
焦らず次のキャリアに進むためにも、最低限の資金は確保しておきましょう。
2. 退職予定日を決める
次に、具体的な退職予定日を決めておきましょう。業務の引き継ぎや有給休暇の消化などを円滑に進めるためです。
退職日は業務のスケジュールや自身の転職活動や準備期間を逆算して計画的に検討します。
年度末など組織の区切りが良い時期を選ぶのが多いですが、自身の状況に合わせて最適な日を設定しましょう。
また、退職予定日を明確にすることで決意が固まり、ずるずると現状維持に流されてしまうのを防げます。
人はどうしても楽な方に流されがちです。
退職日を決めて上司に伝えることで、逃げ道を塞ぎ、確実に次のステップへ進みやすくなります。
3. 次の転職先を確保する
公務員を辞める前に、次の転職先を確保しておきます。無職期間が生じると収入が途絶えるだけでなく、転職活動において不利になる可能性があるためです。
退職後にしばらく自由な時間を満喫し、それからゆっくり転職活動を始める方法もありますが、あまりおすすめできません。
確かに、働きながらの転職活動は負担が大きいものの、内定を得てから退職手続きに入る方が精神的にも安心です。
公務員を辞める際は、事前に転職活動を進め転職先を決めておくとよいでしょう。
転職活動を始めるなら、転職エージェントに登録して、ざっくばらんに話をしてみるのがおすすめです。
おすすめの転職エージェント
公務員を辞めてニートになると直面する現実


ここでは、実際に私が転職先が決まる前に公務員を辞めて、無職になったときに直面する現実を紹介します。
お金が目減りしていく不安
公務員を辞めて無職(いわゆる“ニート”)になると、定期的な収入がなくなり、貯金が目に見えて減っていきます。
たとえ生活費としてある程度の資金を備えていたとしても、収入のない状態で毎月貯金が減っていくのを見るのは、精神的に大きな負担です。
「このままで大丈夫だろうか」という不安は、なかなか拭えません。
だからこそ、家計の収支をしっかり管理し、できるだけ赤字を減らす努力をすることが、精神的な安定を保つ上で非常に大切です。



実際に、私も無職期間が長引くにつれて不安が募り、早く転職先を決めなければという衝動に駆られました。
社会から取り残されている不安
仕事を辞めると、これまで毎日当たり前のようにあった社会との接点が大幅に減少します。
嫌な職場に行かなくてよくなった直後は、開放感を感じるかもしれません。
しかし、そのような自由な気持ちは徐々に薄れていき、代わりに深い孤独感を抱くようになることもあります。
社会との繋がりが希薄になることで、「自分は社会に必要とされていないのではないか」といった強い不安を感じます。
次の就職先を決めずに、勢いだけで公務員を辞めてしまうのは、こうした精神的なリスクを考えると危険な選択と言えるでしょう。



私自身も、もっと計画的に退職すべきだったと、後悔しています。
実際に公務員を辞める前と辞めた後の体験談
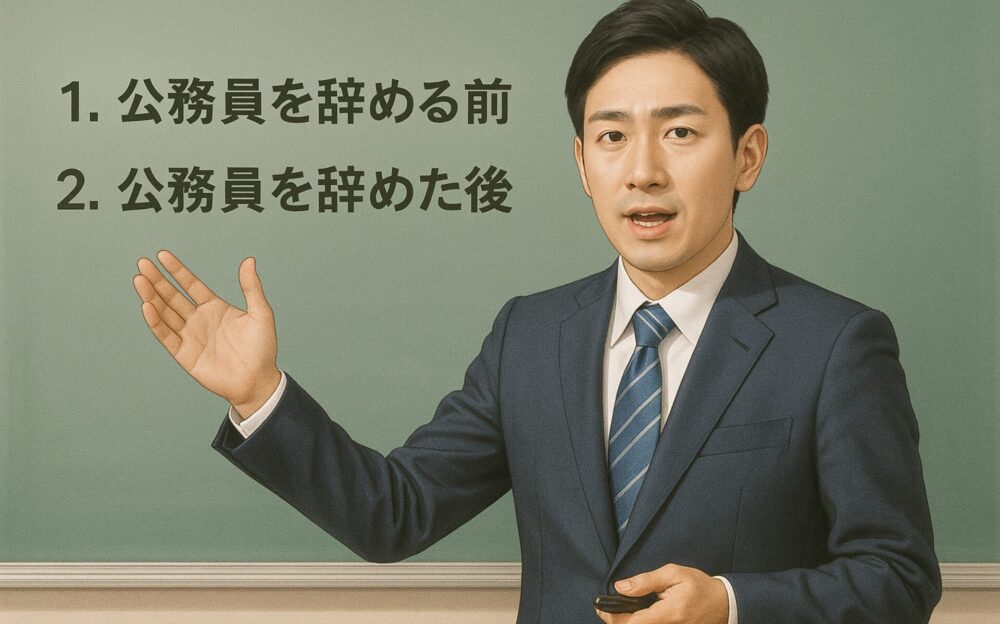
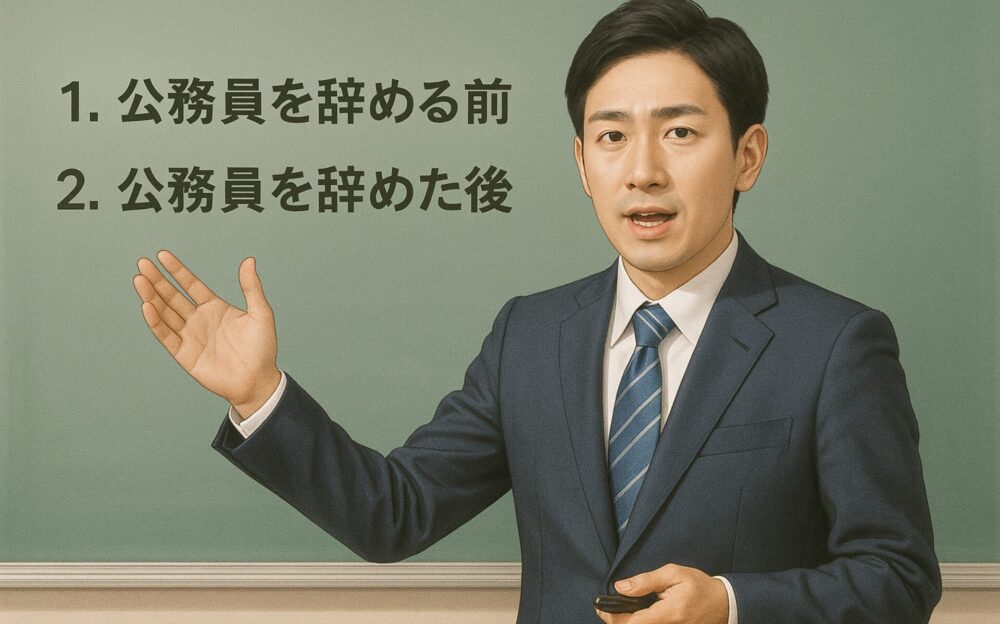
最後に、私が実際に公務員を辞める前とその後の話を簡単に紹介します。
公務員を辞める前の状況
私は市役所で1年、東京都庁で8年の合計9年間、地方公務員として勤務していました。
様々な部署で幅広い業務を経験し、順調に主任試験にも合格。さらに管理職試験の一次試験も突破しており、周囲からも「このまま順調に出世していくだろう」と見られていました。
私自身も公務員として定年まで勤めることが最善だと考えていました。
しかし、安定した身分と将来が見えている一方で、日々の業務に物足りなさや疑問を感じ始めます。「このまま何十年も同じ仕事を続けていいのだろうか」と漠然とした不安を抱くようになりました。
そこで、一念発起して退職を決意します。
退職の意向は退職日の約1か月前に上司に伝えたため、大変驚かれましたが、最終的に理解いただき、無事に退職できました。
公務員を辞めた後の状況
公務員を辞めてから約1ヶ月間は、完全に仕事から離れて自由なニート生活を送りました。
時間に縛られることなく、平日に一人で沖縄旅行に出かけたり、久しぶりに遠方の友人に会いに行ったりと、自分のペースで過ごしていました。
また、平日の昼間に近所のカフェで本を読んだり、何もせずダラダラしたりと、心身ともにリフレッシュする時間を持てました。
退職金があったため、お金の心配はそこまでせずに過ごせましたが、自由に使いすぎた面もあり、気づけば出費がかさんでいました。
その後は、そろそろ仕事を再開しようと思い、転職活動を開始しました。
民間企業に転職後の状況
リフレッシュ期間を経て、未経験ながらIT業界のエンジニア職として民間企業へ転職しました。
公務員とは全く文化もスピード感も異なる世界で、最初は専門用語や開発手法など慣れないことも多く、大変さを痛感する日々でした。
しかし、新たな知識やスキルを学ぶにつれて、少しずつできることも増えていき、仕事の手応えを感じられるようになりました。
そして、約2年間エンジニアとして働いてみた結果、コーディングなどの実装よりも、プロジェクト全体の進行管理やチーム調整などマネジメント業務に強い関心を持ちました。
今後は、これまでの経験も活かしながら、プロジェクトマネージャー(PM)などマネジメント領域へのキャリアチェンジを目指しています。
>>【未経験でプロジェクトマネージャーに挑戦】エンジニアからPMへの転向戦略
まとめ:公務員を辞めたいと考えたら行動を起こそう


「公務員を辞めたい」と少しでも思ったなら、それは自身のキャリアや人生を見つめ直す大切なサインです。その気持ちを無視せず、まずは一歩踏み出してみましょう。
「公務員を辞めたら終わり」という考えは過去のものです。当然辞めることへの不安があるでしょうが、適切な準備でリスクは十分軽減できます。
漠然とした不安を抱え続けるのではなく、「辞めよう」と思った瞬間から具体的な行動を始めることが大切です。
情報収集やスキルの棚卸し、資金計画など、できることから取り組んでみてください。

